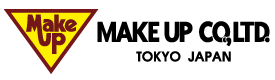当初はくだんのモデルエンジニアエキジビジョンで最も興味を惹かれた“ライブスティーム(トラクション・エンジン)”の図面、キャスティング、旋盤、完成車、キット製造、その他工具の輸入から業務をスタートしました。広告写真家という職業にとっての利便性から使っていた原宿セントラルアパートという立地でそのまま開業した理由は、興味を持たれたお客様に、実際に現物を見て頂き、触れて頂く事が重要だと考えたからです。 ちなみに“メイクアップ”という社名は古い英語で、蒸気機関のボイラーに石炭を投入する時に習慣的に用いられた言葉です。 その後、現在のようなクルマのモデルや組み立てキットを中心に扱うようになり、偶然にも言葉の意味が重なってきたというわけです。
History

『愚直なまでの信条に秘められた遊び心』 山田剛久
メイクアップの植本社長と初めてお会いしたのは1990年頃の事だと思う。時は正にバブル時代、モデル・カーズ誌の創刊号からの読者だった私は、その頃とうとう同誌の編集にまで関わるようになってしまった。もちろん以前からメイクアップのことは知っていた。あまりの敷居の高さに漠然とした憧憬を抱いていただけだが、同社の酒井文雄氏作フルスクラッチ・シリーズ、“マジェスティック・モデル”のポルシェ356スピードスターやジャガーDタイプを誌面で見て、オリーヴサンズ、ウィングローヴ、ブリアンツァ、コンティと云った巨匠たちの作品を凌駕するような逸品モデルカーが、この日本国内でも作られていることが嬉しかったし、そういう趣味世界が我が国でも育まれていること自体に、大きなプライドと希望を感じたことを覚えている。
そんなわけで、当時のメイクアップ=植本さんは、自分にとって畏怖を感じる程の存在だった。しかし運命とはわからぬもので、ある時、自分のような若輩者がメイクアップの編集担当になってしまったのである。無論モデル・カーズ編集部自体が小世帯であり、嘱託だった編集長は通常社内にはいないので、実質たった二人の編集部員でおおよそ全てのことをやらなければならなかった事情もある。正直に書くが、当時の植本さんは畏れられていた。拘りや情熱が尋常ではないので、半端な気持ちで近づくことができなかったのかも知れない。だから寧ろ事情をよくわきまえていない若造を担当に据えてしまえばいいと周囲が画策したのかも知れぬ。事情はともかく、担当になってすぐに決めたのは、新製品をお借りして社内で撮影し、スペシャル・モデルだけのページを作ることだった。
それまでのモデル・カーズでは、プラモデルもダイキャストもスペシャル・モデルも全て一緒くたにして新製品が紹介されていた。クライアントの立場で考えてみれば、これはあまり良くないはずだ。そう思い立って、多分初めて製品をお借りに伺った時だと思うが、帰り際にばったり植本さんとお会いした。この時、初めて拝顔したのだが、雰囲気で社長と解かったので、ご挨拶しなければと焦ったことを思い出す。植本さんは長身のがっしりとした体躯で、噂以上のオーラを放っていた。こんなに大きな人が小さなミニチュア・モデルを愛でるのかとか、そう言えば古い腕時計を蒐集なさっているはずだとか、実物の古いモーターサイクルや英国のスポーツカーがご趣味だったはずだとか、いろんな情報や想いが目まぐるしくの脳裏を駈けめぐる中、緊張の極みで自己紹介をして、名刺を交換させて頂いた。想えばあの日から早や四半世紀が過ぎようとしている。
あの日以来、植本さんを始めとするメイクアップのスタッフの方々にはずっとお世話になってきた。常に良い刺激を頂き、模型やものづくりに関する勉強もさせて頂いてきたと感じている。1/43スケール・キットの常識を覆した“スーペリア・モデル”の電鋳ボディやロストワックス製フレームに驚嘆し、“アイドロン”や“ヴィジョン”といった量産ブランドが立ち上がり、メイクアップ自身が新たなフェーズに入った以降も、その信条に変化がないことに何度も感銘を受けた。そう、誤解を恐れずに言わせて頂くなら、メイクアップの信条には、愚直なまでにブレが無い。
スーペリア・モデルで確立された、マルチ・マテリアルを駆使して精密にディテールを再現する作風や、マジェスティック・モデル等の一品もので鍛錬されてきた丁寧な加工、組み立て、そして伝統的に艶やかな塗装の技法やノウハウは、アイドロン以降の量産ブランドにも確実に受け継がれており、そのアドヴァンテージは他の追随を許さないものだ。それは本当に真面目な仕事と、研ぎ澄まされた感覚の結晶なのである。
製造以前の段階にも惜しみなく時間と手間が割かれていることは言うまでもない。徹底して行われる実車のリサーチ、細部に渡る考証、形状や質感の再現に重点を置いた素材や工法の選択、丹念な原型製作と設計。工業製品と云う制約の中で、如何にバランスの良い、リアリティの有るモデルを作るかが現在のメイクアップのメイン・テーマだ。そしてその製品に対して、世界中から厚い支持と称賛が寄せられているのはご承知の通りである。
ここで植本さんご自身の最近のお言葉をお借りして拙稿の結びとさせて頂きたい。
『精密感という言葉がありますが、精密に作らなければ精密感は出せません。高品質も同様で、一つ一つ丹念な仕事をしなければ品質の向上はありません。我々が思い描く仕事の中で“これだけはやらなければならない”と云う必然的要素と、実車のオーラを掴み取る事によって、結果的に高品質へと至るのだと思います』
これぞ正にメイクアップの信条そのものと言える。そして植本さんを始めとするスタッフの方々は、己自身の愚直さを俯瞰し、なかば呆れ顔で失笑しながらも、その探究をやめようとはしない。その根源を一言でいうなら、それは“遊び心”に他ならないのかも知れぬ。そもそもそれを忘れてしまったら、何も楽しくないことを、趣味人である植本さんは、誰よりもよくご存知だからである。
1978年、東京原宿“セントラルアパート”の一室で産声を上げた弊社メイクアップ。
その歴史は、弊社代表の植本秀行が、英国のウェンブリーパークで毎年行われていた“モデルエンジニアエキジビジョン”に於いて、
彼の地の模型文化に触発されたことからスタートしています。
ここでは当社の歴史を植本自身の回想を織り交ぜてお届けしてまいります。

1970年半ば頃、広告写真家を生業としていた私は、仕事で度々イギリスを訪れていました。
元来イギリスやヨーロッパの自動車、モーターサイクルと云った乗り物に加え、時計やファッション等、あらゆる事象に幅広く興味を抱いていたので、そうした出張の合間に様々なものを見聞して回ることを密かな楽しみにしていたものです。
そんなある時、何気なく立ち寄ったウェンブリーパークで、己の人生の一大転機となる催しを見ることになります。
それは“モデルエンジニアエキジビジョン”という模型のイベントでした。
ここで私は、イギリスに於ける模型の歴史、文化、組織、技術、探究心、そして何よりも本気で模型を楽しむと云う取り組みに多いに心を揺さぶられたのです。
元より模型も大好きでしたので、ここで得た感動を日本に持ち帰り、我が国に於ける模型文化に少しでも寄与したいという気持ちが日増しに大きくなりました。
帰国した私は、その想いを形にすべく、そのころ仕事で使っていた東京・原宿のセントラルアパートの一室で、メイクアップを創業しました。1978年のことです。

さて創業して間もなく、再びイギリスで、現在のメイクアップの基礎になるような運命的なモデルと出会いました。実際その頃のイギリスでは、ホワイトメタル素材を使用したモデル・キットを製造する小規模メーカーが少なからず生まれており、私自身も多いに興味をそそられ、どんな辺境な田舎でも訪ねて行きました。“Big 6”と云う会社もそんな小さなメーカーのひとつでした。同社は元々1/8スケールで“AJS 7R”や“Matchless G45”といったモーターサイクルのホワイトメタル・キットを製造していましたが、私が衝撃を受けたのは箱積みになった 、1/8スケール“Vincent C Rapide Black shadow V-twin 1000cc 1949”のホワイトメタル・キットでした。
もともと私はVincentと云うモーターサイクルに強い憧れがありました。なにしろ1950年代には我が国に2台しか輸入されなかった、それこそ幻のバイクです。薄いやや大判のパッケージを開けさせて頂くと、正に眼が釘付けになってしまいました。そこには完全に分解されたBlack Shadowの部品が整然と並んでいるではないですか。一つ一つの部品がまるで実車をバラした様に正確に仕上げられ、V-twinのエンジンフィンも一枚一枚大変奇麗にキャスティングされていました。先述のAJS 7RやMathless G45のキットとは品質の違いが明白でした。

私はまるで小躍りするような気持ちで、それらの部品に見入りました。モーターサイクルの部品は、或る程度理解しているつもりでした。ダイヤモンドフレーム(クランクケースを含むエンジンをフレームの一部として構成されるフレームレス構造)のVincentだけに、クランクケースと最も特徴的なV-twinエンジンは細部まで徹底的に作り込んでありました。一種のガーターフォークとも云えるフロントフォークは構成もほぼ実車と同様に作られており、やや短いバーハンドルの構成、そして補機類にも大変リアリティがありました。ある意味、作れる人がいるのだろうか?と思える程に細かい部品分割。逆の意味から捉えれば、精密で良質なモデルを作る為に格好の素材。多くのモデルやキットを色々見て来ていましたが、私にとってはそれまでの人生で最も魅力的なモデルだと思えました。
私は即座に購入、輸入したい旨を伝えました。現在と比べてスターリング・ポンドも相当高く、かなりの高額キットでしたが、販売については“後から考えればいいや”と思いました。とにかく、それ程までに私はこのVincentのモデルキットに惚れてしまったのです。しかし、ここで、まさかの事態が発生しました。Big 6の社長は、このVincentのキットは販売できないと言うのです。私は一瞬目の前が真っ暗になってしまいました。意味が良く理解出来ない!!!

よく聞けば、AJSとMathlessはBig6社がプロデュースしたものだが、くだんのVincentはホワイメタルのキャスティングのみを依頼されたものとのこと。そして一般には売らないモデルであるとの説明も受けました。即座に依頼主を尋ねてみると、なんとこのモデルキットの依頼主は、Vincentのオーナーズクラブだったのです。さっそく依頼主であるオーナーズクラブに連絡をとってみましたが、なかなか埒が明かず、二転三転して行き着いた先は、オーナーズクラブの会長でした。
当時は未だ携帯電話も無く、公衆電話はことごとく壊れており、電話をかける場所はホテルか郵便局、又はパブしかありませんでした。三日程を費やして、やっとのことでオーナーズクラブの会長と連絡がとれました。待ち合わせの場所はスコットランド・ヤード脇のパブ。初対面の会長は正に英国紳士で、自己紹介されて驚いたことに、スコットランド警察学校の最高責任者でした。我々はお互いモーターサイクルが好きな仲間として話は大いに盛り上がりましたが、肝心のVincentキットの件はなかなか話が進みません。

よくよく聞いてみると、このモデルは或る彫金師が趣味で制作したもので、今回のモデルキット化は、当時まだ存命であったVincentの創設者=フィリップ・ヴィンセント氏の60歳の誕生日を記念して、オーナーズクラブから彼に贈ると云う趣旨のものでした。また同時に、クラブメンバーのみに配布、販売されると云うモデルで、一般への販売は全く考えていないと言う。それでも会長からは多少建設的な意見を頂き“私の一存では決められないので、クラブメンバーとミーティングをしてから返事をしたい”とのこと。

とはいえ、私の英国滞在期間はあと数日。その後、フランス、イタリアに渡航する予定になっていたので、気持ちは焦っていました。会長とお会いしてから二日後の週末、ご返事を頂けないまま、ご自宅にご招待を受けました。ご自宅にはCラパイドとコメット(単気筒)、それにレストア中のサイドカーがあり、会長のご家族と共に楽しい午后を過ごしました。しかし、Vincentモデルの販売についての進展はありませんでした。結局時間切れとなり、私は諦められないまま大陸に行き、その後帰国の途に着きました。
帰国してから三週間程経過した時、会長から待ちに待ったお手紙を頂きました。コミッションはオーナーズクラブと明記致した上で、メイクアップ社だけに販売すると云う内容!! 早速、最初の200台を注文し、実車のパーツマニュアル、それにあらゆる資料も英国に注文しました。当時は今と違って手紙でのやり取りが主で、往復で2~3週間かかってしまいます。最初のVincentモデルが英国から届いたのはそれから約4ヶ月後の事でした。

このVincentのホワイトメタルキットと出会うことが無ければ、現在の私も、メイクアップも存在していなかったかも知れません。弊社のヒストリーの中で、それほど大切な、重要なモデルキットでした。私は約二ヶ月間掛けて、徹底的にこのVincentを作り上げました。ホワイトメタルをポリッシュして金属の独特の光沢と重量感を出す手法もこの時考えつきました。このキットは一つ一つの部品を丹念に成形し、磨き上げる事によるパズルのような面白さもあり、部品を並べてB全サイズの大きなポスターも制作しました。
その後、弊社は主にイギリス、フランス、イタリア、ドイツ等のマニファクチャーが制作するホワイトメタルやレジン製のモデル(プラモデルやダイキャストモデルと区別する為に“スペシャル・モデル”と云う名称とカテゴリーを打ち出すように努めました)を幅広く扱うようになり、同時にイギリスが誇る至高のモデルカービルダー、“G.A.ウイングローブ”のスクラッチビルド・モデルの取り扱い、そして弊社・酒井文雄によるスクラッチビルド・シリーズ“マジェスティック・モデル”の開発、1/43スケールに於いては当時世界で最もコンプリケートな部品構成と、電鋳ニッケルのボディワーク、ロストワックスのフレームを持つ“スーペリア・モデル”の開発へと“モデル・エンジニアリング”の世界を追求して行くことになります。思えば、それら全てが冒険に満ちた体験でした。